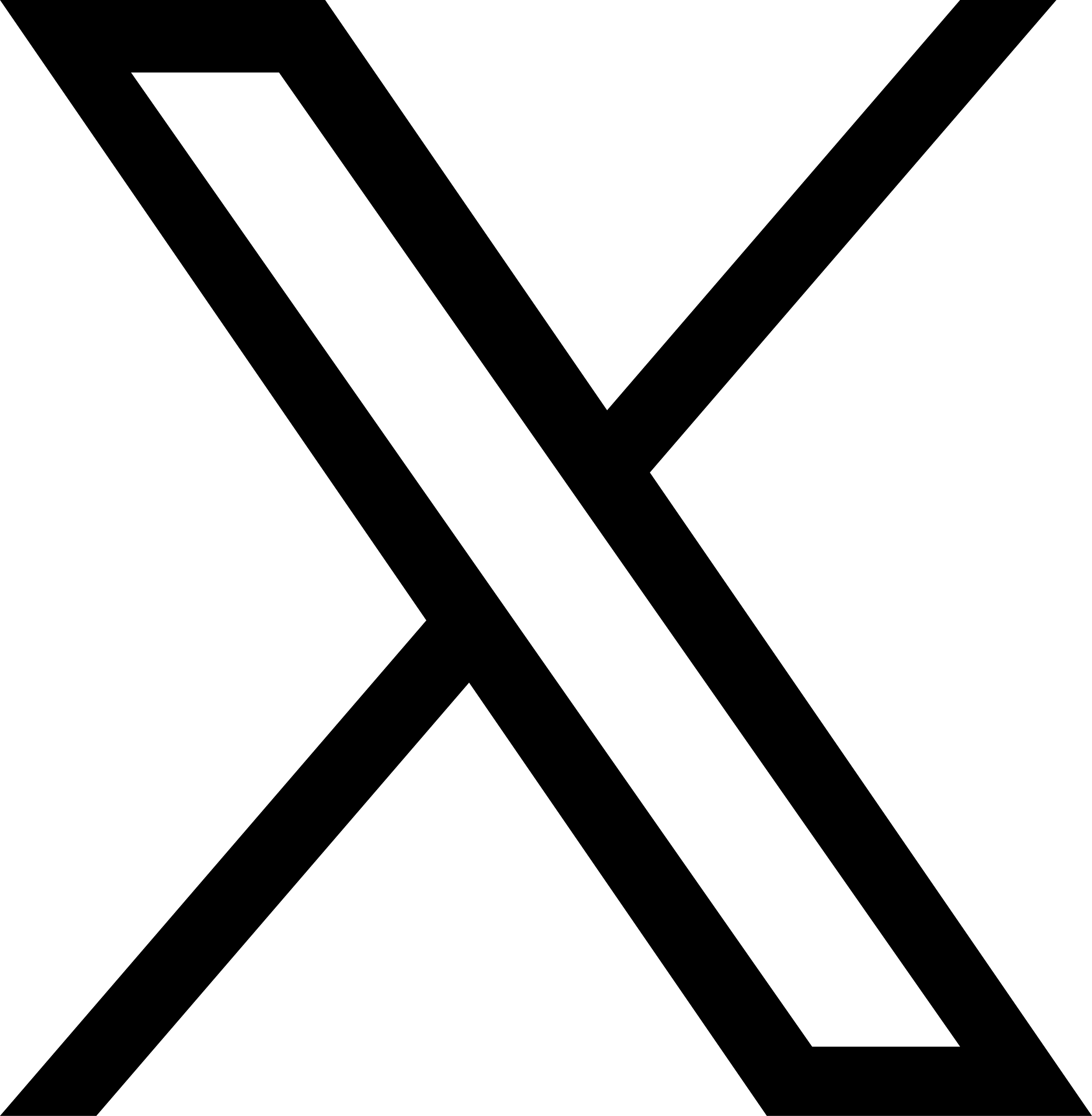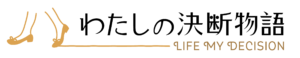23歳のとき、会社員を辞め、医学部受験を決めました。
青森県板柳(いたやなぎ)町の出身で、実家は米とりんごを生産する農業を営んでいました。農家は長男の兄が継ぐことが決まっていたので、次男だった私は何か違う職業に就くのだろうとぼんやり考えながら過ごした幼少期でした。
高校卒業後は大阪大学金属材料工学科に進学。1977年、玉川機械金属株式会社(現・三菱マテリアル株式会社)に入社しました。入社直後は工場勤務で、ヘルメットをかぶりながらさまざまな非鉄金属製品を製造しました。ところが入社半年後の12月、業績悪化の影響か、全社的な希望退職が募集されることとなりました。その数は全体の1割に上るとされ、このまま泥船に残るか、まだ見ぬ大海に出るかの決断を迫られました。
――新入社員として入社して半年で希望退職者を募るなんて、なんて計画性がないんだろう。
そんな不満とともに、このような競争社会で人を蹴落として生きていくことは性に合わないのかもしれない、と感じるようになりました。自分の裁量で仕事ができるような職業で、手に職をつけることのできる仕事がいいのではないか。そんなとき、自分と同じ生年月日に生まれた同期社員と話す機会があり、彼の父親が医療関係の仕事をしていたため、話をする中で「自分は医者に向いているのではないか」と考え付いたのです。
そこで会社を退職し、福島県の会津若松から実家の青森県に戻って、昼は農家の手伝い、夜は自宅で医学部の受験勉強をする日々が始まりました。自分で言うのも何ですが、私は全校生徒1200人もいるような大きな中学校で常に成績は学年トップの優等生。高校では春の選抜高校野球にも出場したことのある町のちょっとした有名人だったので、突然会社を辞めて出戻ったことで街の人たちには非常に不思議な目で見られていました。いろんな噂も飛び交っていましたが、それらにも静かに耐え、1979年に弘前大学医学部に無事合格。卒業後、札幌徳洲会病院で救急医療を学び始めました。
無事医師免許を取得した私ですが、同級生からすれば6年も遅れを取っている状態。大学病院の勤務医で教授として上り詰めていくキャリアはイメージがわきませんでしたし、現場で街の人々に寄り添い手助けする町医者に憧れがあったこともあり、3年の研修医生活を経て、10年分の実力が身に着いたと感じて1994年、40歳のときに下長内科クリニックを開業しました。
八戸市を選んだのは近くの民間病院に勤務していた経験があったことと、南部は津軽に比べて雪が少なく仕事がしやすいと感じたからで、医学部時代に知り合い結婚した妻と二人三脚で病院をスタートさせました。
生活習慣病から高齢者疾患まで幅広く治療し、自分の好きな仕事で患者さんがよくなっていくことがうれしく、あのとき決断をして本当によかったと感じています。23歳で会社員として働いていた頃は、仕事の内容も会社のこともこれからのことも不安ばかりでしたが、大学に入り直して医学の道を志したことで自分の好きな仕事もできているしやりがいもあり、収入も安定しました。会社員だったらいまごろ定年退職ですが、医師になったからこそ71歳でも現役で働けています。
現在は院長として病院経営に携わる一方、血液をサラサラにすることで健康に寄与する仕組みについて書籍にまとめ、啓蒙活動を続けています。自身の体調にも留意しながら、血液をサラサラにする重要性を医師・患者さんともに広めていきたい。あと10年は現役医師として現場に立っていきたいと思っています。
(構成/岸 のぞみ)下長内科クリニック ホームぺージ