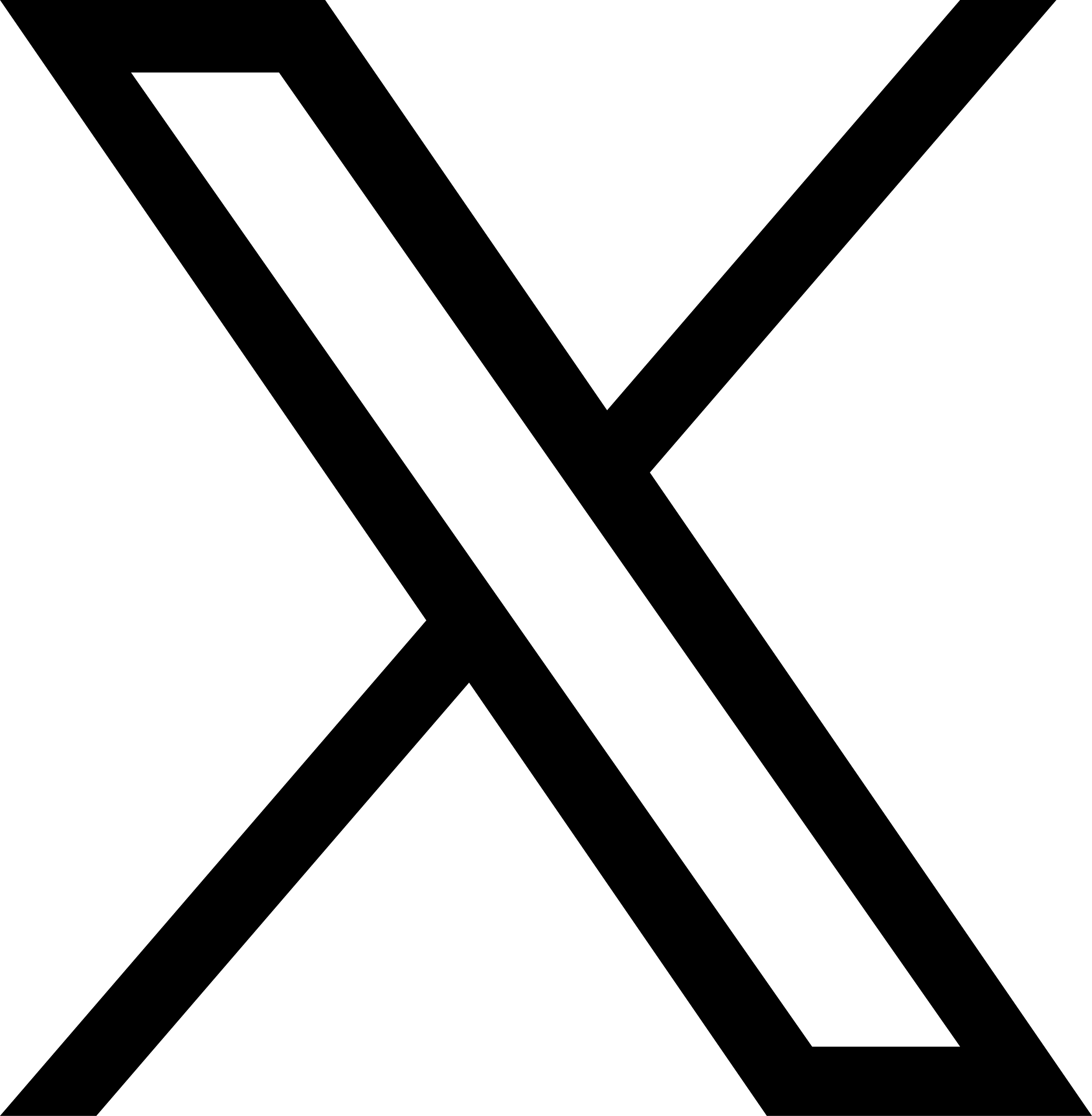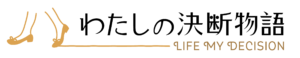写真による生き方学研究家/医学博士/写真家 石原眞澄さん
被写体を決め、構図を決め、シャッターを押す瞬間を決める。写真を撮ることは、さまざまな自己決定の連続だ。そのプロセスがメンタルヘルスに良い影響を及ぼす――それを科学的に解明するために、写真家の石原眞澄さんは研究を続けてきた。
49歳で東北大学大学院に進学し写真の心理的効果に関する実証研究を始め、医学博士を取得。卒業後は愛知県にある国立研究開発法人国立長寿医療研究センターに7年間勤務した。2021年から福岡県糸島市に拠点を移し、写真撮影のワークショップをしたり、写真を使った気分改善プログラムを開発したりする活動を続けている。

たまたま訪れた糸島の海の美しさと食べ物のおいしさに魅了され、2021年に移住した(写真提供:石原眞澄)
息子の病気を機に「幸せになろう」と決めた
なぜ、石原さんは写真によるメンタルヘルスの研究を始めたのか。それは、石原さん自身が20代で心を病み、写真によって立ち直った経験を持つからだ。
電気関係の会社を営む父と専業主婦の母のもとに生まれ、妹と2人姉妹。世田谷区に戸建てを構える、裕福な家庭で育った。
「庭が広くて、植えてあった木に登って遊ぶ、お転婆な子どもでした。その当時から自然の中で遊ぶのが好きで、木の間に座りずっと木漏れ日の中にいたのを覚えています」
小学校から私立に進み、そのままエスカレーターで短大へ。専業主婦が主流の時代、自分も当然専業主婦になると思っていたため、将来なりたい職業を真剣に考えたことはなかった。
短大を卒業後、出身校の事務職として働き、学校の先輩と23歳で結婚。翌年には息子が生まれ、子育てに専念する日々が続いた。
順調に子育てをしていた石原さんだが、いまでも忘れられない出来事がある。息子が3歳のとき、髄膜炎を発症したのだ。石原さんは医師から残酷な宣告を受けた。
「髄膜炎には2種類あり、風邪のように自然と治るパターンもありますが、別のパターンの場合、脳に障害が残る可能性もあります」
医師の言葉を聞いた石原さんは「一度自分が死んだ気持ちになった」と言う。
なかなか現実を受け入れられず、結果が出るまでの1週間は「なぜ息子にこんなことが起こるのか」と怒りや悲しみが交互に押し寄せた。
集中治療室で息子とともに寝ていると、向かいのベッドに障がいを持つ子どもが寝ているのが見えた。
「お母さんもまだ若くて、子どもは障がいを持っているけれど、とても明るくて幸せそうにしていたんです。
それを見て、少しずつ私の気持ちにも変化が起こりました。たとえこの子が目覚めたときに私のことを覚えていなくても、私が息子を産んだことは間違いない。私はこの子と一緒に必ず幸せになる、と決めました。いま思えば自分の人生の中でも大きな決心でした」
写真を撮りながら自分の内面に問いかける
幸い、息子に障がいは残らず、髄膜炎からは無事に回復した。幸せに生きると決めた石原さんだったが、結婚生活は幸せとは言えないものだった。
夫との確執が深まる中、石原さんは心身を病み、朝、夫を仕事に送り出すと、ぐったりして何もできないような状況になる。そんな石原さんを見かねた友人に、「結婚式で撮ってもらった写真が上手だったから、写真でも始めてみたら?」と薦められた。
たまたま、近所の写真スタジオで主婦のための写真講座が開かれており、通い始めたのは石原さんが29歳のときだった。
「友人が勧めてくれたので、写真を始めたい」と話すと、夫はカメラを買ってくれた。いまのように小さな一眼レフはまだなく、大振りのオートフォーカス一眼レフ、CanonのEOS(イオス)シリーズだった。
はじめてカメラを手にした時のことを、石原さんは「嬉しかったですね。すごく嬉しくて写真をたくさん撮りました」と振り返る。

29歳のとき、趣味ではじめて一眼レフカメラを手に取った
講師の写真家は、構図やライティングなど写真の技術そのものを教えるのではなく、「何を撮りたいか」と生徒に問いかけた。
自分はどんな写真を撮りたいのか。写真によって何を表現したいのか。
写真をきっかけに、自分との対話が始まった。公園に行き、そこで遊ぶ子どもや親子の写真を撮らせてもらうこともあった。家族の写真を撮りながら、石原さんは「家族とは何だろう」と考えるようになる。
自分の家族には安らぎはあるだろうか。いまの家族は、自分が本当に求めているものだろうか。
――いまの自分は、幸せではない。
写真を撮りながら、その結論にたどり着いた石原さんは、30歳で離婚を決意した。
お金のために我慢する人生では幸せになれない
協議離婚を経て、息子を連れて実家に戻った石原さんは、これからどのように生きていこうか、と考えた。
「思えば、子育てをする中で、お金のためにその生活を維持してきた部分もあったなと気づいたんです。でも、その結果、幸せにはなれなかった。だったら、今後はお金のために自分の人生を我慢するのはやめよう、と思いました」
そこで純粋に楽しく、好きだと思えた写真を仕事にしていこう、と考えた。しかし、実績があるわけではなく、趣味で写真教室に数年通っただけだ。
「周囲は猛反対でしたよ。そんなので食べて行けるわけないでしょう、と」
でも、「これからはもう、人の意見は聞かない。自分の人生は自分で決める」と石原さんは決めていた。
家の近所の写真スタジオでアシスタント募集の貼り紙を見つけた石原さんは、「これだ!」とすぐに電話した。
面接に行くと、数人の面接官は全員年下。「やる気があってすごくいいと思うんですが、年齢が……」と渋られる。
しかし、石原さんはどうしても、写真で生きていく一歩をつかみたかった。
「まだ何もやっていないのに、年齢だけで可能性を決めてしまうのはいかがなものでしょうか。もし、お客様から年齢の高いスタッフがいると困ると言われたら、即クビにしてもらっていいので、それまで働かせてください」と食い下がった。
その熱意が伝わり、仮採用のような形で働けることになった。
「クビになってはいけないと思ったので、自分の持っている何倍もの力を使ってとにかく一生懸命働きました。
フィルムカメラが主流の時代です。フィルム交換やライティング調整などのアシスタント業務をひたすらこなしました。当時の木製のレフ版は重かったのですが、それを抱えていつも階段を上がっていました。それでも嬉しかったんです。女性だからできないだろう、と言われるのではなく、性別関係なく仕事を頼まれることに、ワクワクしました」
その後、スタジオアシスタントと同時に個人の写真家のアシスタントを続けた。景気の良い時代で、ファッション誌や広告など写真撮影のニーズは多く、アシスタントだけで月収40万円ほどは稼げていた。収入が良いために、アシスタントから抜け出せない人も多かったという。
「私もこのままだとずっとアシスタントだなと思って、あるとき独立しようと決めました」
34歳でスタジオアシスタントを辞め、石原さんはフリーランスのカメラマンとなった。
後編では、その後、石原さんが写真を通じた研究の道へと進んでいく経緯について紹介する。
プロフィール
石原眞澄(いしはら・ますみ)
写真による生き方学研究家/医学博士/写真家
東京都・世田谷区生まれ。写真で心身ともに回復した経験から、科学的な写真の効果に興味を持つ。東北大学大学院医学系研究科脳機能開発研究分野博士課程修了。国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの研究員としてポジティブ心理学にもとづいた独自の写真プログラムの実証研究を開始。高齢者を対象にした研究で気分改善効果を確認し、気分障害やうつ予防、認知症予防への非薬物療法の一選択肢として写真の有効性を実証中。2023年に一般社団法人フォトサイエンス ソサエティを設立。
ホームページ:https://imageworklab.com/