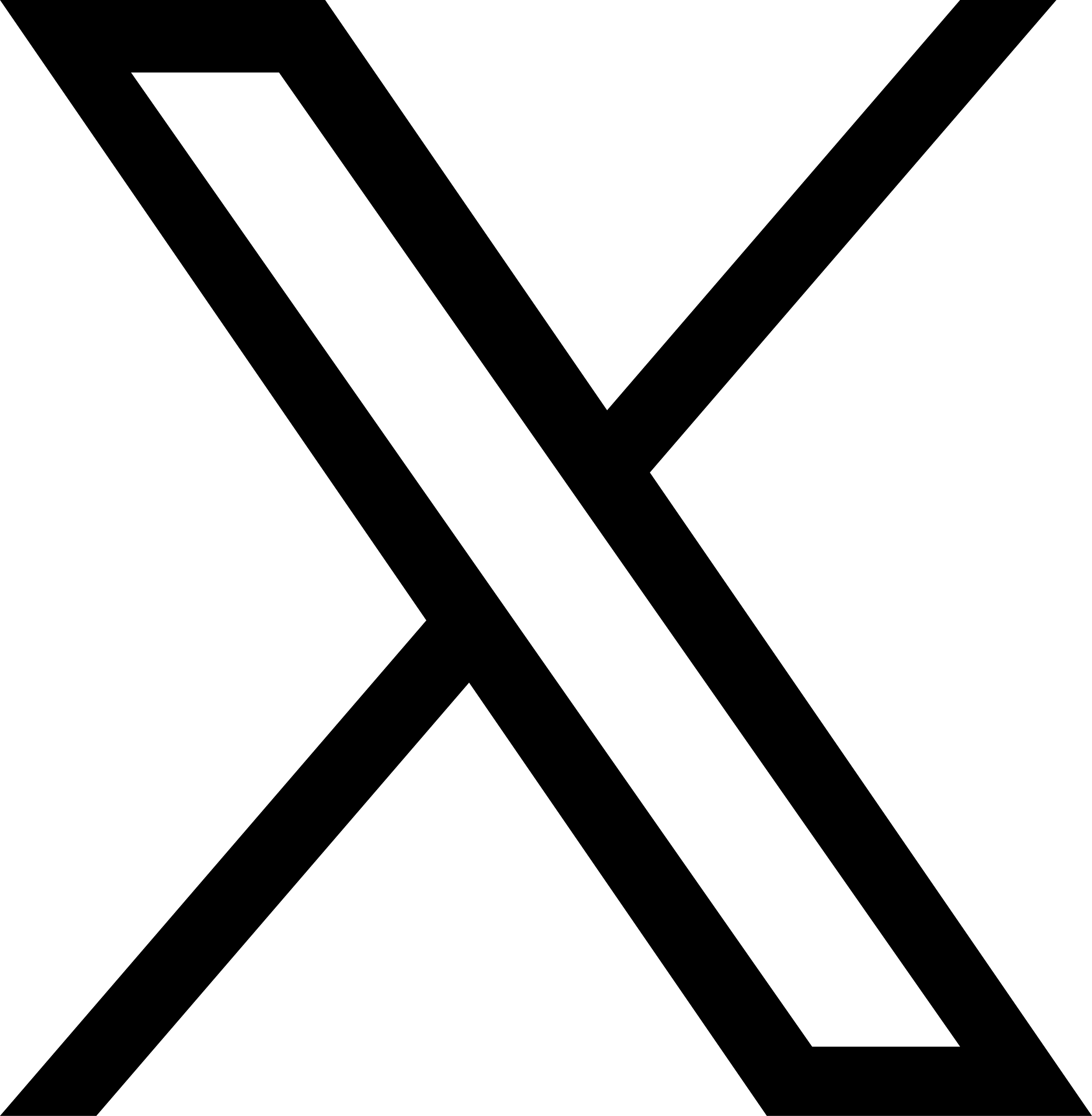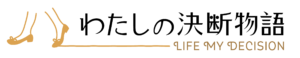![]()
医学部5年生のとき、日本の教育の未来を変えたいと考え、オンライン塾「168塾」の起業を決断しました。
中学生のときに職場体験で病院に行く機会があり、医療の世界に興味を持ったことと、子どものときに3回骨折して整形外科にお世話になった経験から、将来の選択肢の1つとして医師を考えるようになりました。高校生になると生命科学に興味を持ち、医学という学問を学びたいと考えて医学部を目指すようになりました。
学費の負担の少ない国立大学で、研究に強い東北大学の医学部に進学。授業のかたわらで家庭教師と塾講師のアルバイトを始めました。最初はうまく教えられないこともありましたが、生徒の成績が上がったり受験に合格したりして感謝されるようになると、「自分の知識や経験が誰かの人生を変えるかもしれない」と思い、すごくやりがいを感じるようになりました。
ただ、家庭教師や塾講師が生徒と関われるのはせいぜい週に数時間です。受験には5教科必要なのに、英語と数学しか教えられなかったり、宿題を出しても見られるのは1週間後だったり……。これでは責任を持って生徒が望むゴールに導けないのではないかと、指導の限界を感じるようになりました。
1週間×24時間は、168時間。そのうち自分が関われるのは2%にも満たない。自分が直接関わっていないすべての時間をバックアップすることができてはじめて本質的な指導と言えるのではないだろうか。そう考えたのが「168塾」のアイデアの原点です。
当時はまだコロナ禍になる直前で、オンラインでの指導は浸透していませんでした。オンラインでスケジュールや勉強の進捗を共有する仕組みを研究し、まずは家庭教師の生徒から試してみることに。指導以外の時間の勉強の管理をしていくことで、数学で赤点だった生徒が学年1位になるなど目に見える形で成果が出て、手応えを感じることができました。
やがて卒業後の進路を決めなければならないタイミングになり、教育事業で生きていくのか、医師や研究者になるのか、正直悩みました。医学部では、99.9%が卒業後は研修医を経て専門医の道へと進んでいきます。
親に相談したところ、「自分のやりたいことをやりなさい。教育の道に進むにしても、医学部で勉強したことや医師免許は役に立つと思うよ」と背中を押してもらいました。
医学という学問への興味は消えていなかったので、自分がやりたい教育の事業を追求しながら、医師免許も取得しよう、と決めました。
2022年、オンライン塾の立ち上げを考えていた、同じ東北大学の工学部の安部央人(あべひろと)と、教育学部の桑久保皓大(くわくぼこうだい)と3人で168塾を起業。都市部にいない生徒たちでも気軽にアクセスできるように、IT担当の安部が中心となり専用のアプリ開発にも着手しました。1週間の予定を立てられたり、勉強のカリキュラムを作れたり、毎日の勉強の記録を残せたり、わからない問題はアプリから先生に質問ができたりと、盛り込みたい機能がたくさんあり、開発には難航しましたが、約2年の開発期間を経て、2024年9月に完成、一気通貫の仕組みができました。
168塾は勉強の計画から毎日の進捗管理までをトータルでサポートしている塾です。計画づくりから丁寧に関わるのが特徴で、毎日何ができて何ができなかったのかを報告してもらい、講師がそれを見てフィードバックをしています。講師による授業はなく市販の教材を使いながら自学自習をサポートする仕組みで、週1回オンラインで面談もします。メインは高校生ですが、小学生・中学生の生徒もいます。生徒と講師の相性を考慮しながら担当を決めています。生徒とのコミュニケーションが非常に大事なので、将来的には講師チームを心理学や教育に長けたプロフェッショナル集団に育てていきたいと考えています。
いまは医師、研究者、教育事業の3つを掛け持ちしている毎日です。医師としては研修医を終え、週に2~3日は認知症診療を専門にした加齢老年科で医師として働き、研究者としては大学院の医学博士課程で脳科学を専攻しています。今後「脳科学×教育」というテーマで研究を進め、研究内容を教育事業に役立てていきたいと考えています。
日々生徒たちと接していると、将来の目標が明確でない子どもが多いと感じています。なぜ勉強をするのか、何のために大学に行くのか。生徒たちと一緒に考えながら、人生を切り拓いていくサポートができたらと思っています。
(構成/尾越まり恵)
中学生のときに職場体験で病院に行く機会があり、医療の世界に興味を持ったことと、子どものときに3回骨折して整形外科にお世話になった経験から、将来の選択肢の1つとして医師を考えるようになりました。高校生になると生命科学に興味を持ち、医学という学問を学びたいと考えて医学部を目指すようになりました。
学費の負担の少ない国立大学で、研究に強い東北大学の医学部に進学。授業のかたわらで家庭教師と塾講師のアルバイトを始めました。最初はうまく教えられないこともありましたが、生徒の成績が上がったり受験に合格したりして感謝されるようになると、「自分の知識や経験が誰かの人生を変えるかもしれない」と思い、すごくやりがいを感じるようになりました。
ただ、家庭教師や塾講師が生徒と関われるのはせいぜい週に数時間です。受験には5教科必要なのに、英語と数学しか教えられなかったり、宿題を出しても見られるのは1週間後だったり……。これでは責任を持って生徒が望むゴールに導けないのではないかと、指導の限界を感じるようになりました。
1週間×24時間は、168時間。そのうち自分が関われるのは2%にも満たない。自分が直接関わっていないすべての時間をバックアップすることができてはじめて本質的な指導と言えるのではないだろうか。そう考えたのが「168塾」のアイデアの原点です。
当時はまだコロナ禍になる直前で、オンラインでの指導は浸透していませんでした。オンラインでスケジュールや勉強の進捗を共有する仕組みを研究し、まずは家庭教師の生徒から試してみることに。指導以外の時間の勉強の管理をしていくことで、数学で赤点だった生徒が学年1位になるなど目に見える形で成果が出て、手応えを感じることができました。
やがて卒業後の進路を決めなければならないタイミングになり、教育事業で生きていくのか、医師や研究者になるのか、正直悩みました。医学部では、99.9%が卒業後は研修医を経て専門医の道へと進んでいきます。
親に相談したところ、「自分のやりたいことをやりなさい。教育の道に進むにしても、医学部で勉強したことや医師免許は役に立つと思うよ」と背中を押してもらいました。
医学という学問への興味は消えていなかったので、自分がやりたい教育の事業を追求しながら、医師免許も取得しよう、と決めました。
2022年、オンライン塾の立ち上げを考えていた、同じ東北大学の工学部の安部央人(あべひろと)と、教育学部の桑久保皓大(くわくぼこうだい)と3人で168塾を起業。都市部にいない生徒たちでも気軽にアクセスできるように、IT担当の安部が中心となり専用のアプリ開発にも着手しました。1週間の予定を立てられたり、勉強のカリキュラムを作れたり、毎日の勉強の記録を残せたり、わからない問題はアプリから先生に質問ができたりと、盛り込みたい機能がたくさんあり、開発には難航しましたが、約2年の開発期間を経て、2024年9月に完成、一気通貫の仕組みができました。
168塾は勉強の計画から毎日の進捗管理までをトータルでサポートしている塾です。計画づくりから丁寧に関わるのが特徴で、毎日何ができて何ができなかったのかを報告してもらい、講師がそれを見てフィードバックをしています。講師による授業はなく市販の教材を使いながら自学自習をサポートする仕組みで、週1回オンラインで面談もします。メインは高校生ですが、小学生・中学生の生徒もいます。生徒と講師の相性を考慮しながら担当を決めています。生徒とのコミュニケーションが非常に大事なので、将来的には講師チームを心理学や教育に長けたプロフェッショナル集団に育てていきたいと考えています。
いまは医師、研究者、教育事業の3つを掛け持ちしている毎日です。医師としては研修医を終え、週に2~3日は認知症診療を専門にした加齢老年科で医師として働き、研究者としては大学院の医学博士課程で脳科学を専攻しています。今後「脳科学×教育」というテーマで研究を進め、研究内容を教育事業に役立てていきたいと考えています。
日々生徒たちと接していると、将来の目標が明確でない子どもが多いと感じています。なぜ勉強をするのか、何のために大学に行くのか。生徒たちと一緒に考えながら、人生を切り拓いていくサポートができたらと思っています。
(構成/尾越まり恵)
168塾 ホームページ