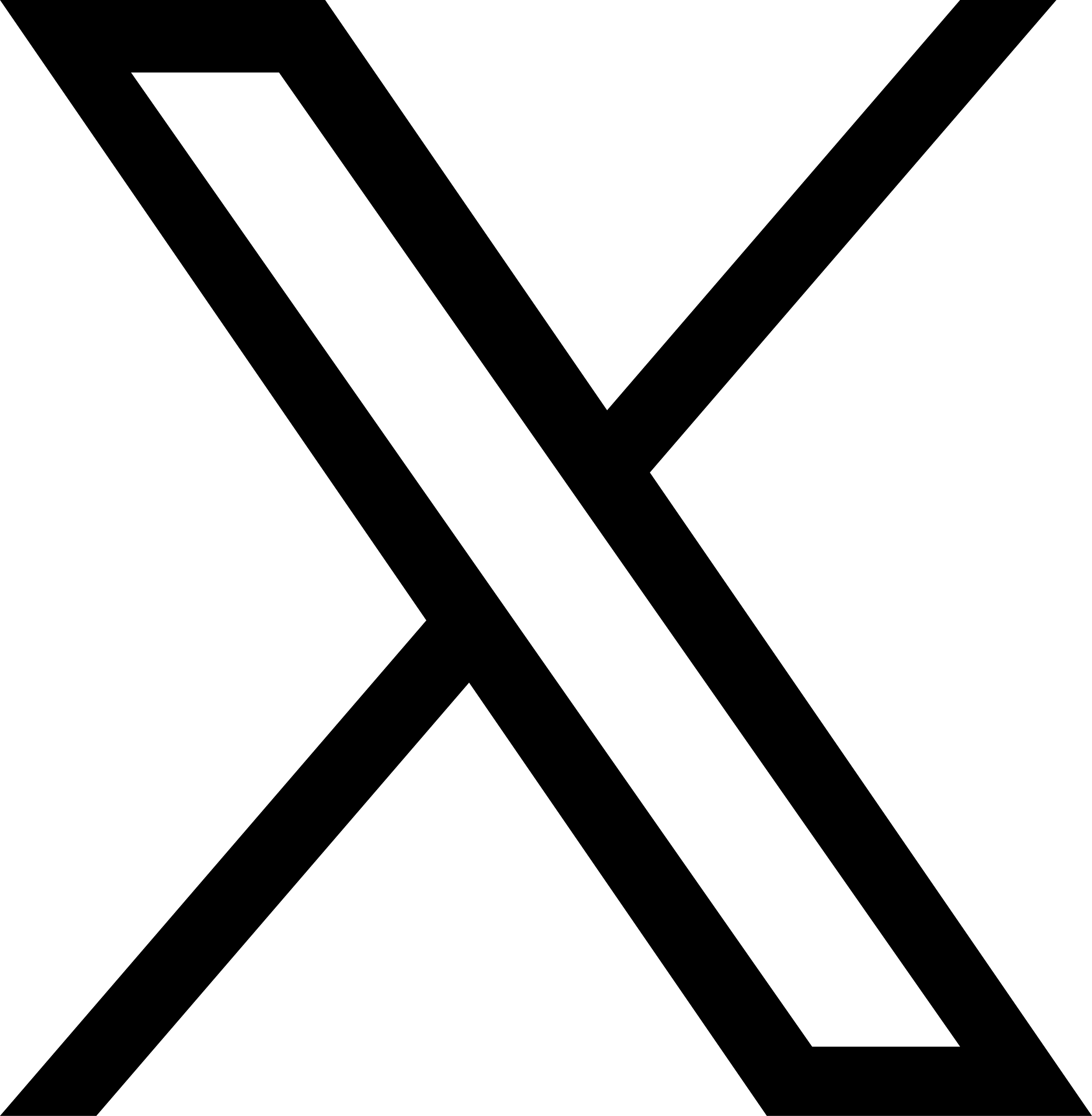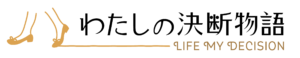41歳のとき、理系研究職の世界から投信会社の世界へ飛び込むことを決めました。
長崎県島原半島の南端、船乗りの街で生まれ育ちました。父はペルシャ湾や中南米諸国と交易をする海外航路の大型船のコック、母親が農家出身だったこともあり、次第に食糧増産に興味を持つように。高校卒業後は筑波大学第二学群農林学類へ進学し、食品や畜産の排水処理に関する環境リサイクルに関する分野を専攻。卒業後は皇太子奨学金奨学生としてハワイ大学の修士課程を修了し、プラクティカルトレーニングという労働ビザが取得できたので現地の水処理ベンチャー企業で働きました。帰国後、文部科学省系の国立研究開発法人で研究員として働きながら、筑波大学農林学系の博士課程に進学。開発法人から給料をいただきながら社会に技術シーズを還元することを目的に研究を続けていましたが、いつまでたっても国からの研究資金に頼って経済的な自立を果たせず、お金に振り回されることにうんざりしていました。
――自分は本当はもっと前向きなチームワークで、実体経済で動いている大きな装置を作り上げたいのではないだろうか。
こうして南九州で畜産廃棄物を利用した再生エネルギー事業を営む水処理大手企業に転職。公的機関から民間企業へ転向しての再出発でした。資源循環という排水処理に関する新事業推進本部で研究もエンジニアリングも担当。ビーカーで試験した結果を30トンの大型バイオリアクターで再現する実証実験を行い、理想通りの廃棄物処理を実現することができるようになりました。社内ベンチャー制度に応募して、お茶殻やコーヒー粕のリサイクルプロジェクトを立ち上げたこともあります。ところが環境ビジネスは理念の受けがいい一方で、どの企業もそこまで潤沢に予算がなく、なかなか購入してはもらえませんでした。20年研究してきても研究者として世の中に受け入れられるものを作れない。研究者としての行く末が見えず、41歳で大きな挫折感を感じ欝々とした日々を送っていました。
そんなある日、さわかみ投信から月次レポートが送られてきました。私はそのころさわかみファンドの受益者、つまり個人投資家だったのです。そのレポートには、「投資を通じて日本の元気を下支えしよう」と書いてありました。今後の長期投資の5つの大テーマとして「水、環境、食糧、素材、エネルギー」が紹介され、さらに投資の知識不問・前歴不問との条件で人材募集をしていたのです。仕事としての投資に興味があったわけではありませんが、そのビジョンに深く共感。「自分が立ち直るには、ここしかない」と思いました。
こうして一念発起してさわかみ投信に転職。環境分野やエネルギープラント分野のアナリストとして働き始めると、業界に詳しいことは大きな強みとなり、新規事業にも携わってきたことで培った企業の設備投資や原価率の決定プロセスに関する知識も大いに役立ちました。先輩アナリストたちや上司も私が培ってきた実体経済での知恵を尊重し、大切にしてくれました。長期投資のアイデアとして自分の意見を採用し環境関連企業に投資してくれる。それは私にとって大きな救いとなりました。
入社3年後の2011年6月、創業者より2代目社長に任命され2012年まで従事。2013年よりベンチャー企業支援業務を経て2015年から経済産業省系の国立研究開発法人で上席イノベーションコーディネータとして産学官連携に従事し10年近くさわかみ投信を離れていました。2022年に復帰し、取締役最高投資責任者に就任しました。さわかみ投信は全国約13万口座の個人投資家と取引があります。それは、今すぐ儲けろという短期的な利益の追求ではなく、長期的な投資を理解している個人投資家の皆さまです。さわかみ投信が黒子となって、社会の大きなうねりも分析しつつ世の中になくてはならない企業を投資先として厳選していく。共にいい社会を作るための三人四脚を実現しています。
日本の個人の金融資産のうち預貯金の額は莫大で、GDPの約2倍のお金が低い利息しか付かない状態で眠っていると言われています。1000兆円の1%でも真っ当な長期投資として動いて、研究やものづくりの現場に前向きなお金の流れが出てくれば、日本経済の長期的成長にとって大きなプラスになると思います。そのような力強い経済を次世代の皆さんに引き継いでいきたいと思っています。
さわかみ投信株式会社 ホームぺージ