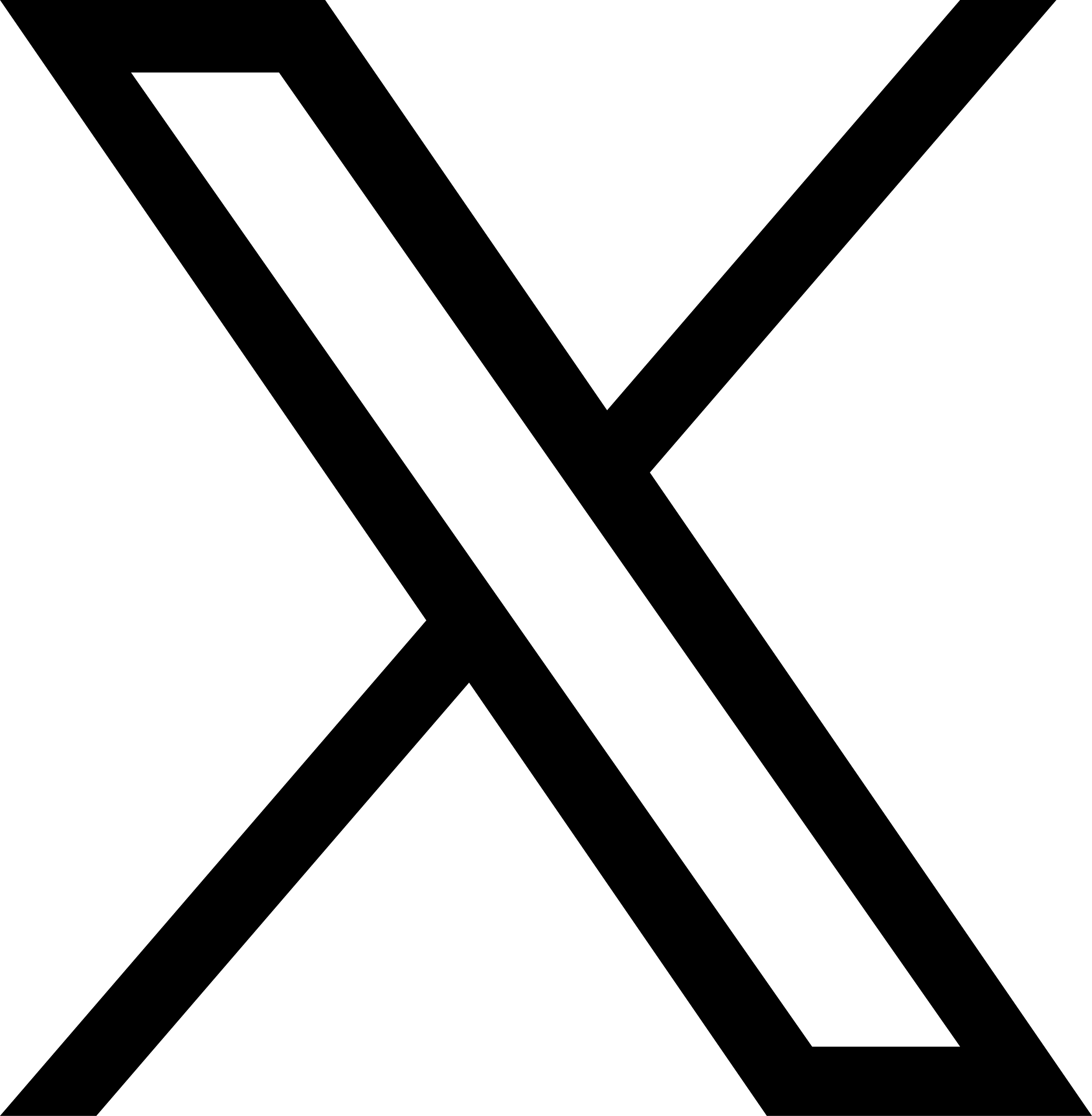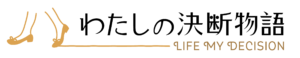私の決断は、ビジネスモデルの転換と大規模なリストラを行ったことです。
兼由は大正初期創業、北海道の根室で水揚げされた水産物の販売を手掛ける老舗企業で、水産加工業を始めたのは父の代からでした。会社を継ぐことは考えていませんでしたが、立命館大学を卒業した2003年はちょうど就職氷河期。結局就職浪人を経て2004年に新卒で兼由に入社しました。
入社後は根室で水揚げされたサケやサケマス、サンマなどを競りで仕入れ、卸売市場で水産問屋に販売する営業部門を担当。当時、サンマは収益確保を支える「稼ぎ頭」で毎年8~11月の繁忙期に得た黒字で閑散期の赤字を補填するという、季節変動型の収益構造に依存している状況でした。
2015年、35歳のときに社長に就任すると海水温の上昇によりサンマの水揚げ量が大幅に減少。さらに2016年にはサケマスのロシア水域における流し網の全面禁止などが相次ぎました。
社長就任当初も売り上げが良かったわけではありませんが、コストカットなどは得意だったので、サンマの漁獲量さえ担保されれば何とかなるのではないかと高(たか)をくくっていましたが、就任前には年間20万トンあったサンマの仕入れは就任時には10万トン、2024年には5万トンに減少するなど、漁獲量が激減。利益を上げることができなくなっていました。
2020年、就任5年目にはビジネスモデルの転換と大規模なリストラは不可避の状況に。工場の電気の使い方や出張時のタクシー代、無駄な残業代カット、昔からやっているという理由だけで続けていた無駄な慣習も根こそぎカットしていきましたが利益率確保には到底至りませんでした。そこで、従業員60名のうち、13名のリストラを決定。外国人労働者だったので管理団体を通じて次の転職先を見つけてからの解雇でしたが、心が痛みました。
さらに、商品そのものにもテコ入れを開始。魚を売るだけでは薄利多売で商売になりません。そこで、魚に付加価値をつけるために2008年頃から発売していたレトルトの煮つけシリーズに注力。これまでサンマしかありませんでしたが、イワシ、サバなどにも横展開していきました。ただし、このような商品を大量生産したところで名前も知らない水産業者の商品を消費者は買ってくれません。そこで、まずは高級感のあるパッケージへと変更し、休眠状態だったSNSアカウントを動かし始めました。根室の天気や街の情報、スタッフのつぶやきなど、街の人が気になる情報をメインに全社員で掲載内容を検討しながら投稿。ホームぺージも改修し、商品情報の掲載も開始しました。
ところが今度は販路開拓のため展示会に出展を、と思ったタイミングでコロナ禍が到来していまいました。2020~2021年は耐えの時期となり、なかなか成果は出ませんでした。口で言うのは簡単ですが、社員の意識づけをするのも大変です。新しいことに挑戦することを社員は嫌がりますし、過去に取り組んできたことをすべて否定されるようで不愉快に思った社員もいたことでしょう。
ですが、これまでの人生を通じて継続していれば何とかなるという自信がありました。商品を多くの人に知ってもらい、利益率の高い商品を売る。時間はかかるけど、シンプルなことです。粘り強く続けていれば道は拓けると信じていました。
すると思った通り2022年頃から徐々に状況が好転し、売り上げベースで微増、利益率ベースでは20%以上改善することに成功しました。レトルト煮つけシリーズも好評で、消費者を意識したマーケティングやセールスプロモーションができるようになったことで、Xのフォロワーも4万5000人にまで増加させることができました。
今後は家族向けのイベントや展示会にも力を入れ、リアルな消費者の意見を聞いて商品開発に生かしていきたい。魚離れが進む日本ですが、一般の方が来場するイベントに出展するとお子様にも「おいしい!」と言ってもらえます。まだまだ勝負できると思っているので、普段魚を食べない方にももっとPRしていけたらと思っています。
株式会社兼由 ホームぺージ