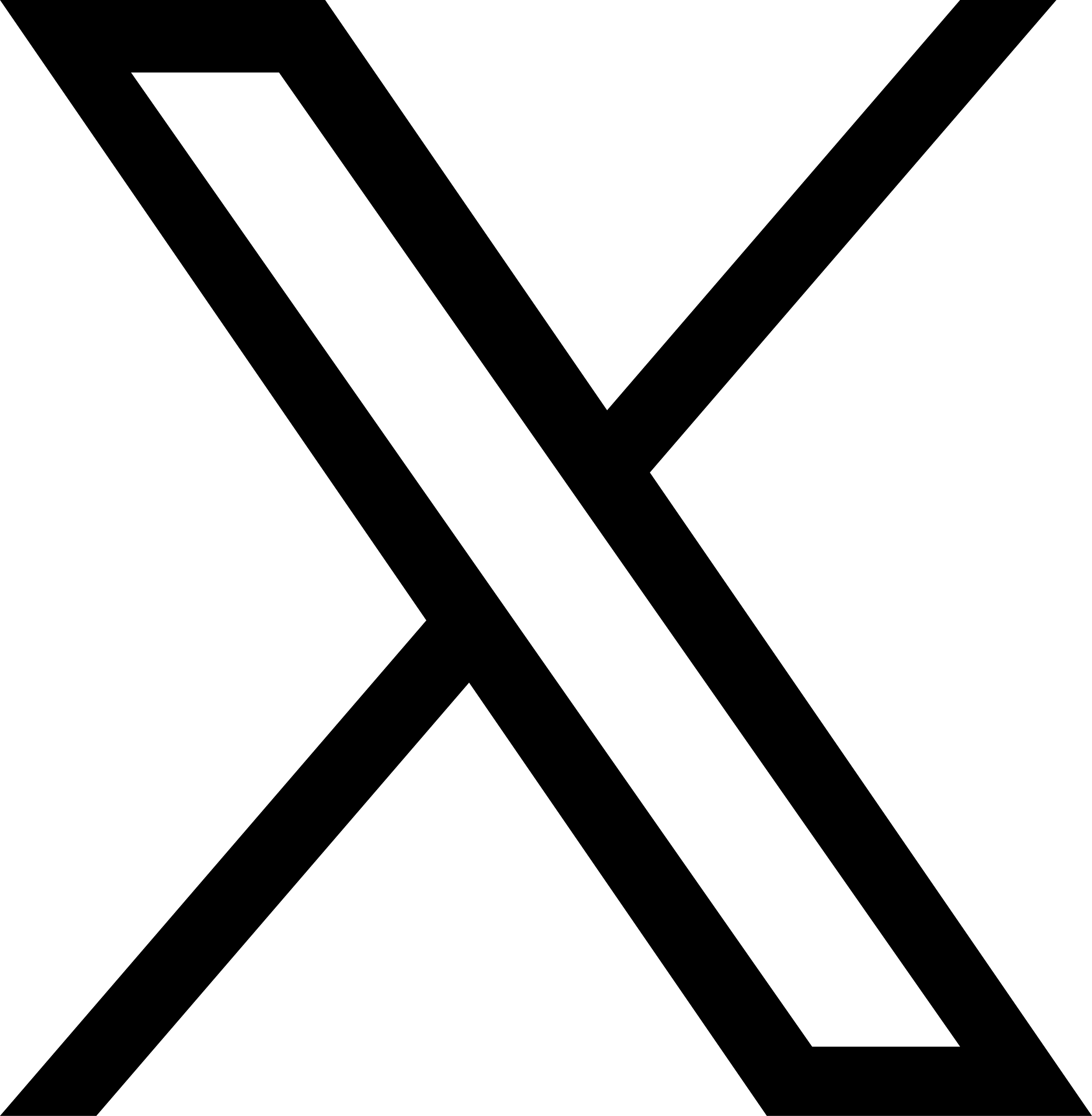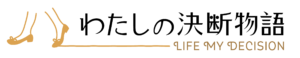私の決断は、39歳で二等無人航空機操縦士の資格を取得したことです。
岩手県宮古市出身で、幼少期から渓流釣りが好きだった私。ルアーなどを作っている釣具店で働きたいと思っていましたが、親のすすめもあり大学進学を決意。大学では土木を専攻し、河川の専門家として川の氾濫シミュレーションの研究に携わりました。北海道の室蘭工業大学大学院修了後、2010年4月に建設コンサルティング業務を展開する八千代エンジニヤリングに入社。河川系の技術者として、河川の氾濫に関するシミュレーションを担当していました。
そんな入社1年目の終わりの2011年3月、東日本大震災が発生。私は東京にいましたが、携帯電話からは地元が津波に包まれている映像が流れてくるのを目にしました。幸い実家は津波の難を逃れましたが、電話がつながるまでに10日ほどかかり、不安な日々を過ごすことに。せっかくインフラ整備の仕事に就いたのだから、こんなときこそ地元のために働きたいと考え、自身で志願し、2年目からは被災した防潮堤・水門を復旧するための設計業務に従事しました。
発災から2年ほど経つと建設コンサルタントが請け負う調査や設計部分は一段落しましたが、復興工事はこれからというタイミング。生まれ故郷にさらに貢献したいと2014年7月から岩手県職員として、岩手県沿岸広域振興局水産部宮古水産振興センター漁港復旧課への転身を決めました。
当時の岩手県の現場は人手が足りておらず、そのため復興の進捗が遅れている状況だったので、これまでの知見を生かして工事全体の調整などに携わりました。その後、工事発注業務や工事監督業務も落ちつき、復興事業の終わりが見えてきた2017年7月より八千代エンジニヤリングに再入社しました。河川の技術者を経てDXを推進する部署に異動となり、デジタルを活用した業務改革を検討することになりました。
そんな折、2024年1月に能登半島地震が発生すると、当社は公共機関や各種協会などの要請に基づき発災1週間後には災害調査のため現地入りをすることになりました。DX(デジタルトランスフォーメーション)の観点から、調査に出向く社員にはデジタルカメラや360度カメラを含めた測量機器を持たせて調査を依頼しましたが、徒歩では先に進めないエリア、上空からでなければ計測できないエリアが多く、今後はリモートセンシングの技術を社内で保有すべきだ、と強く感じるようになりました。
この経験からリモートセンシングに特化したチームの立ち上げを計画し、私は2022年12月に誕生した「無人航空機操縦者技能証明制度」に伴う資格の取得ならびにドローンの飛行申請手順など周辺知識の収集、災害時に使用できる機材の確保を担当していきました。
現状ドローン操作に資格取得は必須ではありませんが、公務員時代に発注者側の視点を学んだことから発注者に安心してもらう意味でも、今後の流れとして資格取得が必須になる可能性が高いという意味でも資格取得は重要であると考え、学科試験ならびに操縦飛行訓練・実技試験を経て、二等無人航空機操縦士の資格を取得しました。そのかいあって、2024年9月に発生した能登半島豪雨では、いち早く現地入りし、ドローンを使い現場の被災状況をリモートセンシング技術で三次元化し、石川県と共有することができました。
二等無人航空機操縦士の資格取得には専門のスクールに通って30万円ほどの費用がかかることから、会社に提案し、資格取得費用を会社に補助してもらえる仕組みにしました。また、自らの学んだ技術を会社全体で横展開できるように会社公認のドローン実地講習会を企画・実施、ドローン技術・知識の啓もう並びにリモートセンシング技術の普及に尽力しています。
現状ではドローンを飛行させるための法規制や機材の取り扱いのハードルがまだまだ高いため、弊社社員の中でドローンを操縦できる人材や必要な関連知識を有した人材は多くありません。しかし、今後はドローンの規制緩和や低価格化が進み、ドローンがより身近なツールになり、スマートフォンやデジタルカメラと同じように誰もが現場に持っていけるツールになると思っています。そのため、これからもドローンをはじめとしたリモートセンシング技術の普及を推進していきます。合わせて、個人としては一等無人航空機操縦士の資格取得も目指していきたいと思っています。
八千代エンジニヤリング株式会社 ホームぺージ