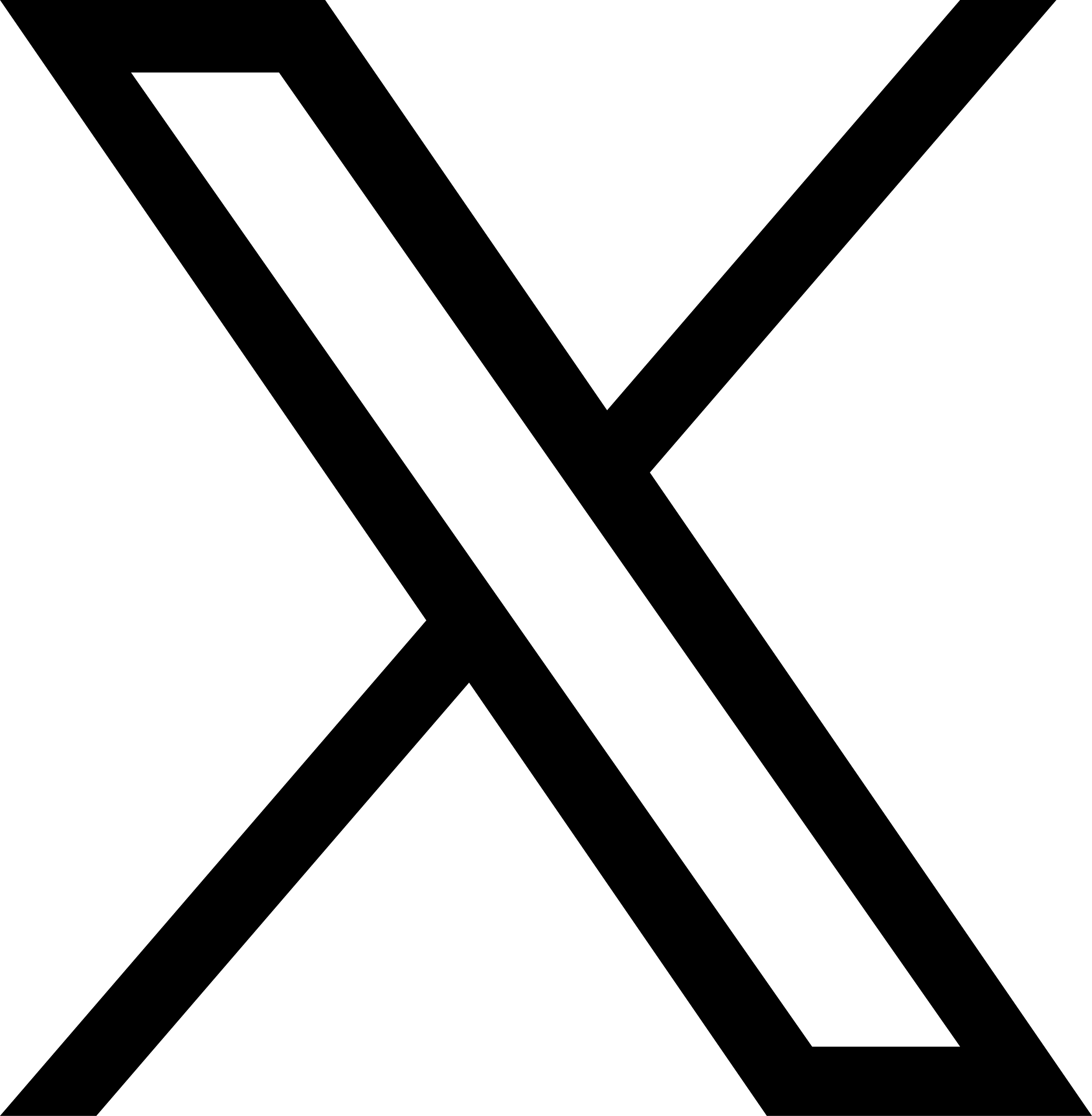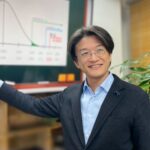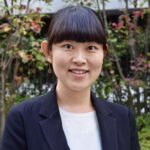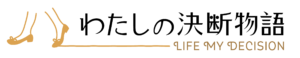写真による生き方学研究家/医学博士/写真家 石原眞澄さん
離婚を機に、スタジオアシスタントとしてカメラの世界に入った石原眞澄さん。前編では、石原さんの生い立ちや写真を撮り始めた経緯を紹介した。アシスタントから独立して写真家として活動した後、写真が心を癒す効果を科学的に検証したいと考え、研究の道に進んだ石原さん。写真とともに生きてきた半生をいまどう受け止めているのか、話を聞いた。
石原眞澄さんは写真のスタジオアシスタントとして働いた後、34歳でフリーランスのカメラマンに転身した。
「最初の頃は出版社に営業に行っていました。カメラマンにはそれぞれ得意とするジャンルがありますが、私は『生ものが得意です』とよく言っていましたね。人物や料理の写真を撮ることが多かったです」
そして、40歳を過ぎた頃から、出版社などから請け負って撮影をするだけではなく、フォトセラピーのワークショップの開催や、自分が伝えたいことを写真で表現して個展を開く写真作家としての活動も並行して行うようになった。
海外にも興味があったため、文化庁の新進芸術家海外留学派遣制度のスカラシップを獲得して渡米。写真家のリンダ・コナー氏のもとで 1年間、古典技法を学んだ。
また、「エクスプレッシブ・アートセラピー」の創始者のナタリー・ロジャース氏にフォトセラピーを紹介する機会を得て、交流することができた。
「アリゾナやユタでソロキャンプをしながらネイティブアメリカンのペトログラフ(岩に刻まれた絵)を大型カメラで撮影するなど、アメリカでの作品作りの日々はとても刺激的でした」と石原さんは振り返る。
大学院で写真と心理学を研究