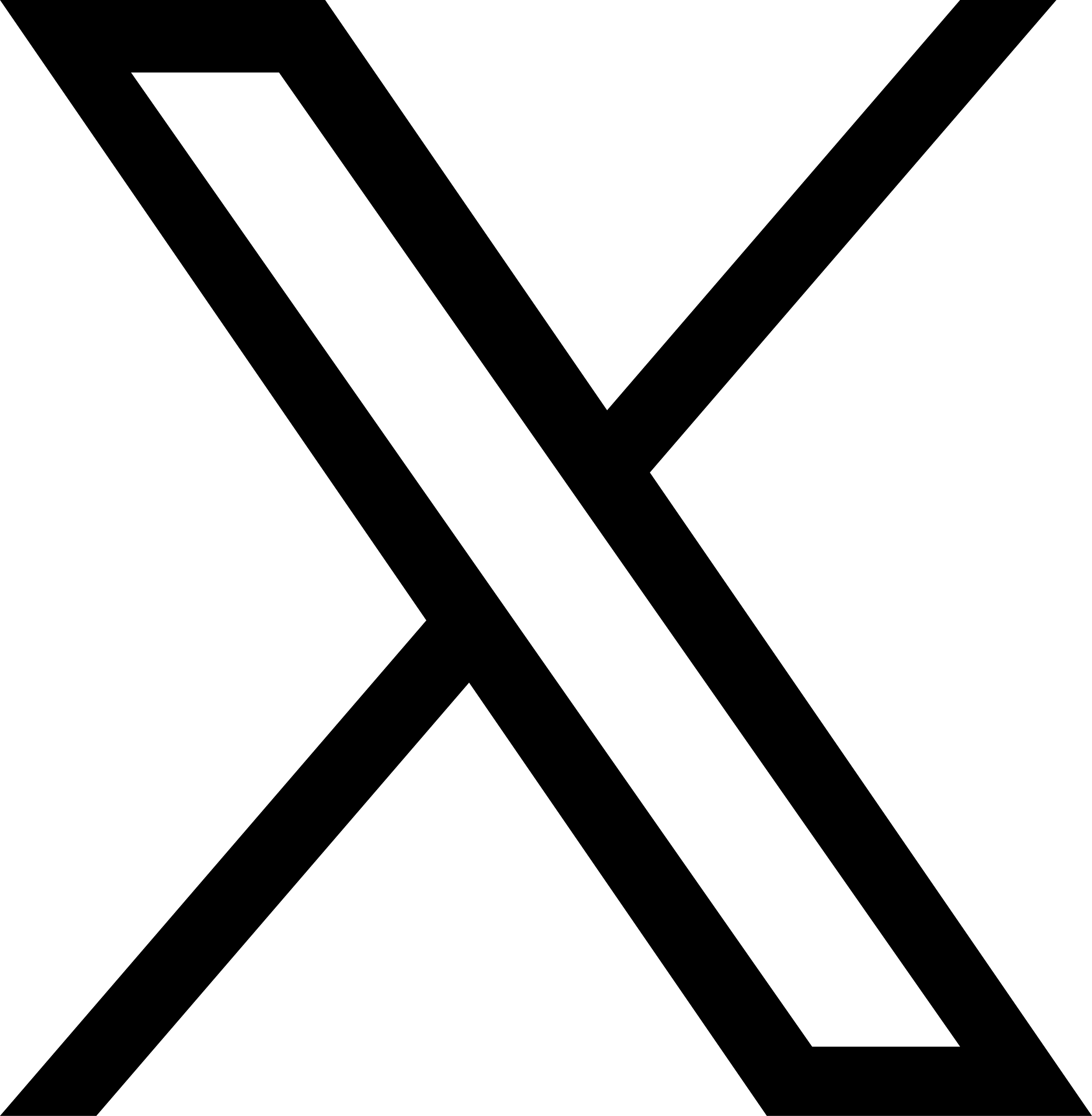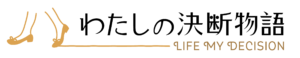1社依存体制から脱却し、多品種少ロットの銅加工専門工場へと方針転換をしたこと。これが私の決断です。
関西学院大学商学部を卒業後、蝶理(ちょうり)という繊維の専門商社に7年間勤務。下着生地などの営業を担当した後、30歳で父が経営する畑(はた)鉄工株式会社に入社しました。業績は右肩下がりで、父親からも「もう事業を畳むかもしれない。継ぐ決断は慎重にしたほうがいい」と言われていました。しかし「挑戦してみたい」という気持ちもありましたし、何より当時数名いた従業員の雇用を守りたいと考え、専務取締役に就任。父親が病気に伏せてしまったこともあり、翌31歳のときには実質的な経営権を握ることとなりました。
畑鉄工は祖父が創業した会社で、部品を製造して鉄道会社に納める金属加工事業会社でした。主な取引先はユアサ コーポレーションで産業用電池部品の製造販売を手掛けていました。ところが、2004年に日本電池とユアサ コーポレーションが経営統合してジーエス・ユアサコーポレーション(GSユアサ)となったことで取引が激減。それまで一度も赤字になったことがありませんでしたが、2005年に私が入社したタイミングでは決算書を一目見ただけで「入社は失敗だったかも」と思ってしまうほど経営状況は悪化していました。
それでも自社最大規模の得意先だったのはGSユアサでしたが、今後これ以上の取引拡大は見込めないことは明らかでした。新規取引先の開発が急務だったため、さまざまなメーカーを回っては頭を下げ、新たな取引につながる糸口を探していました。すると、銅の加工業者がいないという声をさまざまな場所で耳にしました。銅の加工品は大量ロットでの発注が少なく、多品種少ロットでの発注となり手間がかかるため、どこの工場もやりたがらなかったのです。
GSユアサからは大量ロットでの発注となるため、工場ラインもシンプルで効率的です。一方、銅の加工を請け負うとなると、少ロットのため納期の短い案件も多く、工場ラインの切り替えも複雑で対応が非常に難しい。悩みましたが、銅加工を極めればブルーオーシャンが開けるのではないかと考え、思い切って受注を銅加工に絞り、銅加工専門業者として成長していくことを決断しました。2006年のことです。
もちろん社内からは「そんなのは無理だ」「非効率だ」という反対意見も出ましたが、経営状況が悪いことは誰もが理解するところでした。このときに去って行った人もいましたが、改革しないといけないこともわかっていた。始めてみると案外すぐに仕事が増え、順調に売り上げも伸びていきました。当初は効率的な運用がわからずに連日深夜まで作業してもらっていましたが、2009年のリーマン・ショックの際に受注が減少した際、効率化に関するさまざまなアイデアを募集。新たな機械の導入や人材採用にも注力し、効率化を図っていきました。結果、取引先は5社から300社超へ、そして営業利益は2005年の660万円の赤字から2025年には1億9000万円の黒字にV字回復。競合企業が少ないために見積もりが通りやすく、劇的に営業利益を改善することができたのでした。
2015年、39歳で改めて代表取締役に就任。翌2016年には認知度アップのために「銅加工.com」というWEBサイトを立ち上げました。銅や銅加工についての記事を発信しており、ユニークユーザー数が毎月1万人、ページビューが2万あるオウンドメディアに育てることができました。2022年には現状に即したキャッチーな社名に変更したいと考え、ハタメタルワークスに改称。コロナ禍で工務店が暇を持て余していたこともあって、安く新社屋を建設することができました。
1社依存はリスクでしかありません。大口取引先からの受注減、リーマン・ショック、コロナ禍とさまざまな苦難がありましたが、ピンチをチャンスと捉えてさまざまな挑戦をしたことでここまで来ることができました。現状は1社あたり最大でも全体の2割以下となるよう取引先数を拡大しており、安定的に利益を出すことができるようになりました。今後は若い人たちが働きたいと思える会社にできるよう、さらなる改革に取り組んでいきたいと思います。
株式会社ハタメタルワークス ホームぺージ