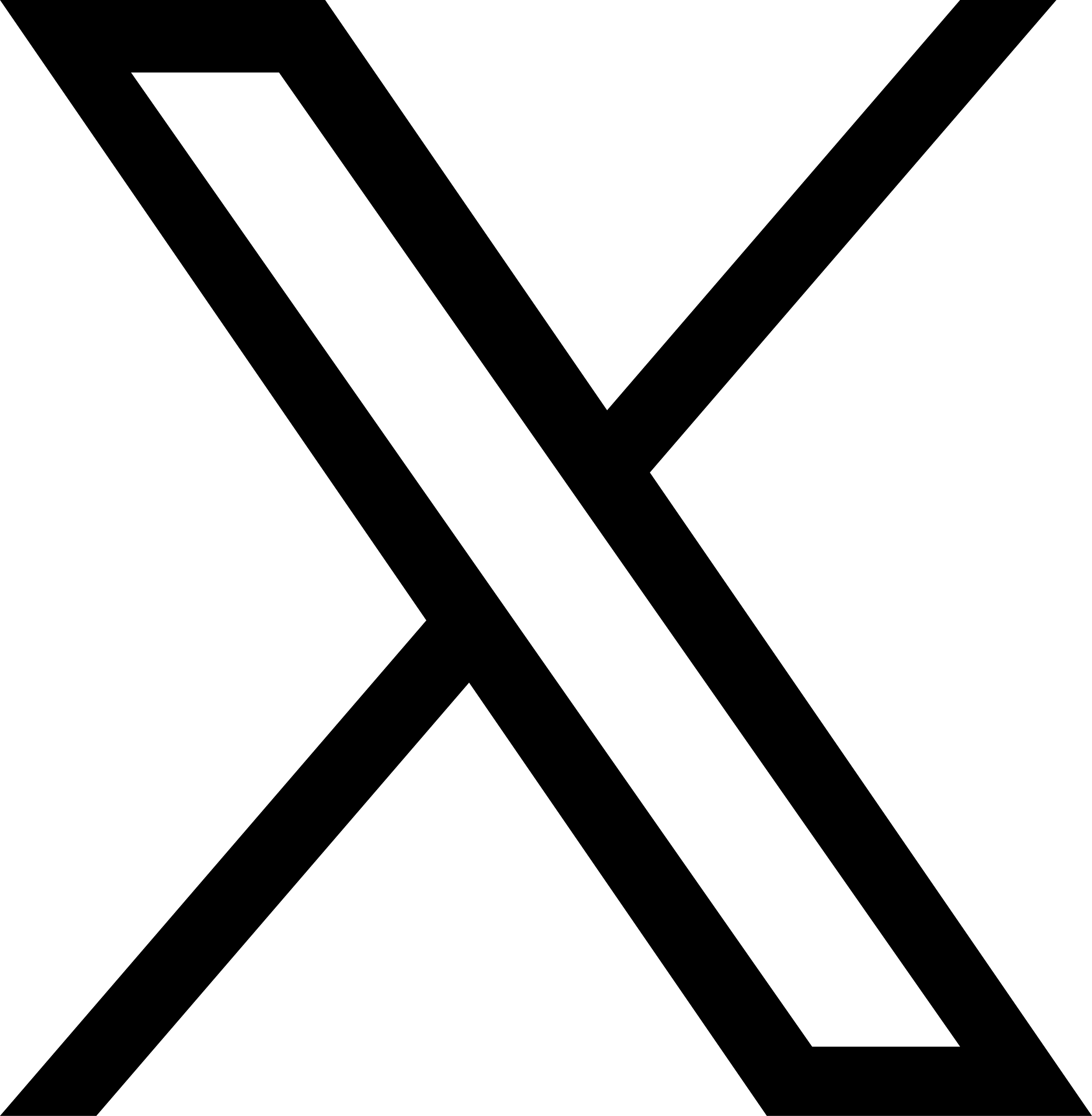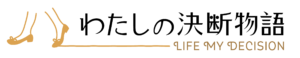一般社団法人スポーツコア 代表 川上優子さん
川上優子さんは兵庫県神戸市で生まれ、両親の離婚を機に3歳からは熊本県に移った。「常に走っている、絵に描いたような活発な子どもだった」と言う。
1人っ子で、祖母と母と3人で暮らした。生活を支えるために母親が忙しく働いていたため、自立心が芽生えるのは早かった。
「母は私が自分で何でもできるように意識して育ててくれたのだと思います。例えば、服を着るときにボタンが止められなかったとしても、手を出さずに私ができるまで待っていました。当時母はまだ20代で、自分がその年齢になったときに、母のすごさを実感しましたね」

活発な子どもだった(川上さん提供)
小学生のときはハンドボール、ソフトボール、バドミントン、バスケットボール、水泳とあらゆるスポーツを経験。当時からすでに負けず嫌いの性格が際立っていた。
「どのスポーツでも一番になりたくて、一生懸命プレイしていました」
中でも、ハンドボールに夢中になった。
「でも、小学6年生くらいで気付いてしまったんです。私、性格的にチームプレイに向いていないな、と。負けず嫌いだから、試合終了のホイッスルが鳴る瞬間まで戦いたいのに、負けている試合でチームに諦めムードが漂うことに耐えられなかったんです」
そんなときに、小学校の先生がチームを組んでくれて出場した駅伝大会で、前を走る選手をごぼう抜きした。
「8番目くらいでスタートしたのが、全員を抜いてトップになったんです。前の人たちをどんどん抜いていくのがすごく楽しくて。自分が頑張った分だけ結果が出るのがいいなと思いました」
――駅伝で日本一になりたい。
川上さんの中に、大きな夢が生まれた。中学で陸上部に入り、本格的に陸上に打ち込んだ。夏場は800メートル、1500メートルなどの中距離、冬は駅伝で3~5キロ。ここで、勝負の厳しさにも直面する。
「楽しいなと思って始めた陸上でしたが、いざ部活で本格的に走ってみると、『楽しい』という感覚よりも試合前の緊張や不安と戦うことがつらいな、と感じるようになりました。負けたくないけど、試合に出れば負けることもある。その悔しさとの戦いでもありました」
迷いが深まった高校時代
高校は、熊本県の陸上強豪校の熊本信愛女学院高校にスポーツ特待生として進学。高校で、走ることに対する悩みが深まっていった。
「私はなぜ走っているんだろう、と悩むようになりました。おそらく人生ではじめて経験した挫折だったと思います」
高校2年生で大きなケガも経験。練習にも身が入らなかった。
「練習に行かず、近くの公園でパンを食べて、時間をつぶして家に帰るんです。私は一体、何をやっているんだろう……と、半年間くらい悶々と考えていました」

結果が出ず、ケガも多かった高校時代。陸上を続けるかどうか、悩んでいた
高校3年生のインターハイも予選落ちに終わり、周囲からは、陸上はもう続けないだろうと思われていた。川上さん自身も、「大学に進学して体育の先生になるのもいいな」と考えていたが、いざ進路を決めるタイミングで、「実業団に入って陸上を続けたい」と考えるようになる。
「やっぱり、走ることを諦められませんでした。私は要領のいいタイプではないので、勉強と陸上の両立は難しいだろうと思って、大学の陸上部ではなく、実業団で陸上に集中できる環境を選びました」
実業団に入って陸上を続けるという覚悟が決まってからは、練習に対する姿勢も変わった。そうすると、結果が伴ってくる。高校3年の秋の国体では予選を突破し、3000メートルで自己新記録を更新した。
「インターハイで予選落ちした選手が国体で4位になったので、あいつは誰なんだ?と、まわりがかなりザワついていました(笑)」
オリンピック決勝で猛ダッシュ
宮崎県に拠点を置く宮崎沖電気の実業団に入団し、寮生活が始まった。
「高校時代は顧問の先生の家に下宿していたんですよ。4~5人が同じ部屋で2段ベッドで寝ていたので、集団生活には慣れていました。実業団の寮はワンルームの個室で、部屋にキッチンもバス・トイレもあり、パラダイスだー!と思いました」
朝練の後、数時間仕事をしてまた練習する毎日。実業団の練習量の多さ、厳しさに驚いた。朝は毎日10km、まるでレースのように競い合い、遅れた選手は振り落とされていく。夕方は会社から競技場までの6kmを走って行き、練習後また6km走りながら寮に戻る。
「もう必死です。日曜日だけ完全に休みなのですが、疲れ果てて最初の頃は一歩も外に出られませんでした。練習が終わった後の6kmが走れなくて、歩いて帰ることもありました」
川上さんが厳しい練習に耐えられたのは、「駅伝で日本一になる」という目標があったからだ。目標を叶えるためには、チームのエースになる必要がある。現状の実力とのギャップを埋めるため、川上さんは必死に食らいついた。
夢に手が届いたのは、入社から3年目のことだった。1996年、全日本実業団女子駅伝(現在:クイーンズ駅伝)で最長の5区を走り、区間新を出し、沖電気宮崎を初優勝に導いた。
「子どもの頃からの夢が叶った瞬間だったので、今でもいちばんうれしかった記憶として残っています。この大会での記録が、その後のレースの記録にもつながっています」
この結果に勢いをつけ、この年、米アトランタオリンピックの出場権も手にする。
21歳で臨んだ、はじめての世界の舞台。
「それまで海外に行った経験も少なく、あまりに非現実的で、すべてが夢物語のようでした」
しかし、アトランタの選手村に入ったとき、川上さんのコンディションは絶不調だった。
「自分でも驚くような記録を出してオリンピック出場権を獲得したので、走り方がわからなくなってしまったんです。いままでなら簡単に出ていた記録すら練習でも出せなくなっていました。自分でもどうしたらいいかわからないまま出国して、現地に行っても調子が上がってこない。トレーナーさんに体を見てもらって、ようやく少し調子が上がってきましたが、選手村の部屋で、ずっと帰りたい、と思っていました」
そんな川上さんだったが、本番では持ち前の底力を発揮する。
「昼間は暑いので、スタートは夜です。予選の日、スタジアムに入ると観客は満員で、フラッシュがたかれて、すごい歓声が聞こえてきたんです。普段、日本の陸上大会でここまで満員になることはないので、その景色に感動して、やばい、これは絶対に決勝に行きたい、と思ったんですよね。気が付いたら先頭を走っていて、みんなもそんなことある?ってビックリしていました(笑)」
そして迎えた決勝の舞台。1万メートルを走り終えるまでの時間は約30分。その間、川上さんは冷静に思考をめぐらせた。
「よく考えたら、これオリンピックなんだよな、って。そう思ったら簡単に諦めるのはもったいないなと思ったんです。でも、コンディションはそんなに良くないから、最初から飛ばしてもきっと最後までもたない。ゴール前の1000メートルだけ死ぬ気で走ろう、と決めました。ダッシュを始めてからの記憶はほとんどありません」

アトランタオリンピックの決勝(川上さん提供)
残り2周半で川上さんは猛ダッシュをかけ。結果、7位となり5位の千葉真子さんとともに入賞。長距離トラック種目で日本人の女子選手が2人同時に入賞したのはオリンピック史上初の快挙だった。
しかし、川上さんの中には悔しさが残った。
「万全の体調で120%の力を出しても届かないのがオリンピックです。だからこそ、4年後、また絶対に戻ってこよう、と閉会式で自分に誓いました」
そして4年後、川上さんは再びオリンピックの舞台に戻ってきた。本番2週間前、豪シドニーの選手村に入り、レースに照準を合わせていく。

シドニーオリンピックの予選(川上さん提供)
「予選を突破しなければ決勝に出られないので、やっぱり予選が一番きついですね。心が折れそうになりましたが、これまで自分を応援してくれた人をがっかりさせるわけにはいかない、という一心で走り切りました」
予選を通過し、決勝進出を果たしたが、結果は10位。アトランタオリンピックの記録には一歩及ばなかった。
「2度目のオリンピックは、少し楽しむ余裕もありました。アトランタオリンピックの閉会式では、4年後に必ず戻って来たい、と考えていましたが、シドニーオリンピックのときは、4年後もオリンピックに行くものだと思っていたので、特別な感情はありませんでした」
しかし、シドニーから戻って2年後、川上さんは突然陸上から引退し、ゴルフに挑戦することを表明した。
なぜ、そのような決断をしたのか。後編ではその理由をひも解いていく。
(文/尾越まり恵 特記のない写真/齋藤海月)プロフィール
川上優子(かわかみ・ゆうこ)
一般社団法人スポーツコア 代表理事
1975年熊本県生まれ。1994年、熊本信愛女学院高等学校卒業後、沖電気宮崎に入社。1996年アトランタオリンピック女子10000m7位入賞、2000年シドニーオリンピック女子10000m10位と2大会連続でオリンピック出場。全日本実業団対抗女子駅伝大会では、OKI(当時の沖電気宮崎)の3度の総合優勝にも貢献した。
2002年に陸上を引退し、ゴルフに挑戦。2018年から23年までキヤノン アスリート クラブ 九州のコーチを務める。2017年に一般社団法人スポーツコアを設立し、代表理事に就任。現在は講演活動・イベント出演、ランニング教室など幅広く活動する。